この記事のポイント
・専業主婦でも年金分割により、夫が納めた保険料を考慮した額の年金を受け取れる
・年金分割の対象は厚生年金なので、夫が国民年金のみ加入の場合は年金分割ができない
・年金分割されるのは、支給額ではなく「婚姻期間中に夫が納めた厚生年金保険料の納付実績」
専業主婦が離婚する場合、経済的な点で不安を感じることが多いでしょう。
特に、夫がいなくても老後に十分な年金を受け取れるのか、不安を感じてはいませんか?
かつては、本人が納めた年金保険料のみを年金額の計算の基礎としていました。
そのため、専業主婦本人が納めた年金保険料は基本的に少額であることから、離婚した専業主婦が受け取れる年金額が少ないという問題がありました。
しかし、現在は「年金分割」といって、夫が婚姻期間(結婚している期間)中に納めた厚生年金保険料の半分を、離婚した妻の年金額の計算の基礎にできるようになっています。
離婚するなら、老後の生活も含めて経済的に困窮することがないように備えておくことが重要です。
そこで、このコラムでは、年金分割の概要や注意点について解説します。
離婚した専業主婦でも年金を受け取れる?
離婚した専業主婦でも、「年金分割」により、婚姻期間中に納めた夫名義の年金保険料を考慮した額の年金を受け取れます。
「年金分割」とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に支払った保険料を分割する制度です。
ただし、離婚すれば必ず夫の年金を分割してもらえるわけではありません。
「年金分割」は、あくまでも厚生年金(共済年金を含む)を対象にした制度であるため、夫婦ともに国民年金のみに加入している場合、年金分割の対象にはなりません。
夫の職業によって加入している年金の種類が違うため、分割可能かどうかにも違いがあるのです。
そもそも、国民年金の加入者は、第1号被保険者から第3号被保険者に分かれています。
第1号被保険者:自営業者や学生、フリーランサーなど
第2号被保険者:会社員や公務員
第3号被保険者:2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の妻や夫(例:専業主婦や専業主夫)
そして、年金は一般的に、下の図のような3階建ての構造で説明されます。

次の2つのパターンを見てみましょう。
1.夫が学生、自営業、フリーランスの場合
2.夫が会社員、公務員の場合
(1)夫が学生、自営業、フリーランスの場合
夫が学生、自営業、フリーランスの場合、夫は国民保険の第1号被保険者です。
そして、第1号被保険者の配偶者(例:専業主婦)もまた第1号被保険者であり、各々で国民年金保険料を納めます。
この場合、離婚したとしても夫名義の年金を分割することはできません。
(2)夫が会社員、公務員の場合
夫が会社員や公務員の場合、夫は第2号被保険者です。
この場合、夫は国民年金に加えて厚生年金に加入しています。
したがって、離婚した場合、夫の厚生年金が年金分割の対象となります。
夫の厚生年金部分を婚姻期間に応じて夫婦で分割し、それぞれが受け取るべき年金額を計算します。

なお、この場合も、1階部分の国民年金は分割の対象になりません。
あくまで厚生年金部分のみが年金分割の対象です。
<ワンポイント> 厚生年金と共済年金の一元化
2015年10月1日から共済年金は厚生年金に一元化されましたが、かつて公務員は厚生年金ではなく、共済年金に加入していました。
しかし、年金制度の一元化を図るため、公務員も共済年金ではなく厚生年金に加入する形に変更されています。
年金分割には2種類ある
年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。
それぞれの概要や利用するための条件について、一緒に見ていきましょう。
(1)合意分割制度
「合意分割制度」とは、婚姻期間に応じて、その期間の厚生年金の標準報酬を最大2分の1まで分割できる制度です。
合意分割制度では、年金をどのくらいの割合で分割するかは夫婦の話合いで決めます。決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
合意分割制度を利用する条件
「合意分割制度」を利用するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
・ 2007年4月1日以後に離婚等をしたこと
・ 婚姻期間中に標準報酬月額、標準賞与額などの厚生年金記録(共済組合の組合員である期間を含む)があること
・ 当事者双方による合意があること
(合意できない場合は裁判手続により按分割合を決定していること)
・ 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年)を経過していないこと
(2)3号分割制度
「3号分割制度」とは、3号被保険者(扶養されていた妻や夫)から請求することで、2008年4月1日以後の婚姻期間中の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
この制度を利用するために元配偶者との合意などは必要なく、第3号被保険者単独で請求できます。
ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。
3号分割制度を利用する条件
3号分割制度を利用するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
・ 2008年5月1日以後に離婚等をしたこと
・ 2008年4月1日以降の婚姻期間中、国民年金第3号被保険者であった期間の標準報酬月額、標準賞与額といった厚生年金記録があること
・ 請求期限(原則として、離婚した日の翌日から2年)を経過していないこと
年金分割における3つのリスク
年金分割の制度がなかった時代、専業主婦にとって離婚はハイリスクでした。
しかし、「年金分割」の制度ができたことで、離婚へのハードルは低くなっているといえます。
ただし、年金分割には次の3つのリスクがあるので注意が必要です。
1.年金の全額が分割されるわけではない
2.期限を超えると原則、分割を請求できない
3.遺族年金は受け取れない

離婚に踏み切る前に、これらのリスクを確認しておきましょう。
(1)年金の全額が分割されるわけではない
「年金分割」されるのは婚姻期間中に支払った年金保険料の納付記録のみです。
さらにそのうち、厚生年金または共済年金のみが分割対象であり、国民年金や企業年金は対象外となります。
| 年金の種類 | 内容 | 受け取れる人 | |
|---|---|---|---|
| 1階部分 | (老齢)基礎年金 | 受け取る金額は年金の種類にかかわらず、一定額となる。 | 国民年金の加入者 |
| 2階部分 | 報酬比例部分 | 年金保険料が給与額をもとに決まるため、給与が高いほど保険料が高く、年金額も高くなる。 | 厚生年金や共済年金の加入者のみ |
| 3階部分 | 企業年金 | 会社ごとの上乗せ年金。同じ金額の年金を受け取れる確定給付年金と、同じ金額の保険料を支払うが、受け取れる年金額は年金の運用実績により左右される確定拠出年金がある。 | 厚生年金や共済年金の加入者のみ |
なお、企業年金は、1年以内に受給予定であるなど、受給できる可能性が高い場合には、財産分与の対象になると考えらえています。
(2)期限を超えると原則、分割を請求できない
年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して原則2年です。
職探しや新居探しなど、離婚後の新しい生活環境を整えていると、2年は意外と早く経ってしまいます。
請求期限まで2年もあると思わず、早めの行動をおすすめします。
(3)遺族年金は受け取れない
離婚により、遺族厚生年金を受け取ることはできなくなります。
そのため、年金分割で年金の一部を受け取れたとしても、遺族年金を受け取れないことにより、トータルでの年金受給額が減ってしまうこともあります。
【まとめ】夫が会社員や公務員なら、夫の厚生年金の分割を請求できる!
年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に支払った保険料を分割する制
度です。
ただし、厚生年金(共済年金を含む)を対象にした制度であるため、夫婦とも
に国民年金のみに加入している場合には対象にならない点にご注意ください。
なお、年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあり、
それぞれ分割割合の決め方が異なることを覚えておきましょう。
年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して原則2年です。
また、離婚すると遺族厚生年金を受け取れなくなります。
離婚を検討中であれば、離婚後の生活に備えておくことが重要です。
離婚における年金分割でお悩みの方は、離婚問題を取り扱う弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、離婚後の生活設計を考えておくとよいでしょう。
その他、離婚については「離婚のご相談時によくある質問」をご覧ください。
アディーレでは、宮城県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
仙台にお住まいの方で、離婚相談をお考えの方はアディーレにご相談ください。
【対応エリア】仙台市青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市など



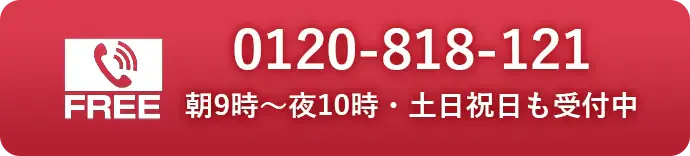
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。